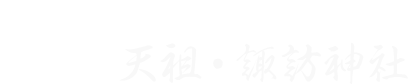生命の言葉と戌の日|令和7年4月
『橋本 左内』
志(こころざし)を立つ
橋本 左内(はしもと さない)
天保五年(1834)三月十一日現在の福井藩奥外科医(藩医)の長男として生まれる。名は綱紀(つなのり)、通称を左内とし、号を景岳(けいがく)とされた。安政六年(1859)十月七日斬首の刑に処せられた。享年二十六。
十五歳の時、偉人英傑の言行や精神を学び『啓発録』を著した。その内容は「去稚心(ちしんをさる)」「振気(きをふるう)」「立志(こころざしをたつ)」「勉学(がくにつとむ)」「択交友(こうゆうをえらぶ)」の五つの項目を立てて、少年にして学問を志す者の為に、入門の手引として作られた書である。
神道知識への誘(いざな)ひ
氏神(うじがみ)と産土神(うぶすながみ)
日本全国の神社には、さまざまな神さまが祀られています。その中でも「氏神」と呼ばれる神さまは、とりわけ私たちの日常生活に関わりの深い神さまといえるでしょう。
氏神とは、もともと古代社会において血縁的な関係にあった一族がお祀りした神さま(一族の祖先神あるいは守護神)をいいました。
しかし、中世においては土地の神さま、つまり鎮守の神さまである産土神(産土とは生まれた土地という意味で、その土地を守護してくださる神さま)までが、氏神と混合されるようになりました。現在では氏族と関係なしに、住んでいるところの祭祀圏内である神社を氏神神社としています。
住まいのところの氏神神社を調べるには、その土地に古くからお住まいの方、町内会や自治会の会長やご年配の方にお聞きになってみてください。また、東京都神社庁のホームページで都内の近くの神社を、地図上やキーワードで検索できるページを用意しています。この機会にぜひご活用ください。
神社は心のふるさと 未来に受け継ごう 「美(うるわ)しい国ぶり」
4月の「戌の日」| 11日(金)・23日(水)