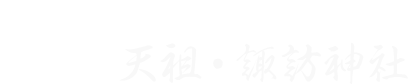生命の言葉と戌の日|令和7年9月
『紀 貫之』
やまとうたは 人の心を
種として よろづの言の葉とぞ
なれりける
「やまと歌」(和歌)は
人の心を種として
それがさまざまな言葉と
なったものである。
紀貫之(きの つらゆき)
平安前期の歌人。三十六歌仙の一人。加賀介、土佐守などを歴任木工権守(もくのごんのかみ)に至る。醍醐天皇の勅命で「古今和歌集」撰進の中心となり、仮名序(かなじょ)を執筆。
歌風(かふう)は理知的で技巧にすぐれ、心と詞の調和、花実兼備(かじつけんび)を説いて古今調をつくりだした。漢詩文の素養が深く、『土佐日記』は仮名文日記文学の先駆とされる。
神道知識への誘(いざな)ひ
古今和歌集
平安初期の最初の勅選和歌集。二十巻。醍醐天皇の勅命により、紀貫之・紀友則(きのとものり)・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)・壬生忠岑(みぶのただみね)の四人の撰者が編集して奏上した。仮名と漢文で書かれた二つの序文がある。
詠み人知らずの歌と六歌仙、撰者らおよそ百二十七人の歌千百十一首を四季、恋以下十三部に分類して納めたもの。短歌が多く、七五調、三句切りを主とし、縁語、掛詞など修辞的技巧が目立つ。優美繊細で理知的な歌風は、組織的な構成とともに後世へ大きな影響を与えた。
神社は心のふるさと 未来に受け継ごう 「美(うるわ)しい国ぶり」
9月の「戌の日」| 2日(火)・14日(日)・26日(金)